知られざる偉人伝
鷗外と漱石
性愛表現の分水嶺 その2
夏目漱石
(小説家、評論家、英文学者/1867-1916)

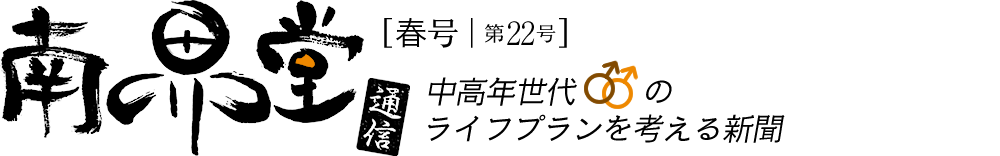
鷗外と漱石
性愛表現の分水嶺 その2
夏目漱石
(小説家、評論家、英文学者/1867-1916)

前回は1909年(明治42年)に発表された鷗外の小説『ヰタ・セクスアリス』が、主人公の性愛経験がアッケラカンと包み隠さず語られているゆえに発禁処分となったことをみた。その5年後に発表されたのが夏目漱石の『こころ』。この作品は漱石の小説のなかでも最もよく読まれているらしいから、近代日本文学最大のベストセラー小説といってよいかもしれない。しかしこの作品はいろいろと謎めいたものを秘めた小説なのだ。
謎の第一は、この作品が語り手である「私」に宛てた「先生」の長い手紙で唐突に終わっていて、手紙を読んだ「私」がそれをどう受け止め、その後どう生きたか、まったく語られないことである。前半は主人公の語り、後半は「先生」の語り、これで終わり。ひょっとすると漱石は三人称の語りでその後の主人公の人生を書きたかったのかもしれないが、それは果たされなかった。先生からの遺書ともいえる衝撃的な手紙を読んだ主人のその後は、完全に読者の想像に委ねられているのである。近代小説の醍醐味が主人公の成長ぶりを読者が追体験するところにあるとすれば、「漱石先生、これはあんまりでは……」と愚痴を言いたくなるのは私だけではないだろう。
第二の謎は、「先生」と「私」のあいだには明らかに恋愛に似た、強烈な魂の交流らしきものが育まれていくのだが、世の評論家たちがそうした事実をほぼ完全に無視してきたところにある。「私」が鎌倉の海水浴場で先生と初めて親密になるきっかけをつかんだとき、主人公は「二丁ほど沖へ出ると、先生は後ろを振り返って私に話し掛けた。広い蒼い海の表面に浮いているものは、その近所に私ら二人より外になかった……私は自由と歓喜に充ちた筋肉を動かして海の中で踊り狂った……」と語る。これに応えるように、先生は長い手紙の中で、「私」との関係が深まっていく日々を邂逅しながら「……あなたは私の過去を絵巻物のように、あなたの前に展開してくれと迫った。私はその時心のうちで、始めて貴方を尊敬した。あなたが無遠慮に私の腹の中から、或る生きたものを捕まえようという決心を見せたからです。私の心臓を立ち割って、温かく流れる血潮を啜ろうとしたからです……私は今自分で自分の心臓を破って、その血をあなたの顔に浴びせかけようとしているのです。私の鼓動が停まった時、あなたの胸に新しい命が宿る事が出来るなら満足です」と書く。これが愛の告白でなくて何であろう、と私は思うのだが、評論家の先生方の見方はどうも違うらしい。
この作品が「ホモ丸出し」の小説だと喝破したのは作家の橋本治であったが(『蓮と刀』河出文庫)、こうした見解は一部の研究者を除いてほぼ無視されてきた。最近になって作家の島田雅彦が同様のことを書いて(『深読み日本文学』インターナショナル新書)話題になっているが、ほぼ30年のあいだ橋本の見解は無視されてきたことになる。
橋本は続けて、大胆な仮説を立てていた。漱石は最初、先に引用した部分が同性愛的な感情の吐露であるとは気付かず、気付いたとき「あっ、これはヤバイかも」と思ったが、新聞の連載小説だったから書き直すわけにもいかず、にっちもさっちもいかなくなって先生の長い手紙兼遺書というかたちで解決をはかるしかなかった、という仮説である。
さすが漱石先生、「先生」の手紙の文学的価値は疑いようがない。とりわけ「先生」が友人Kと「御嬢さん」との三角関係にはまりこんで煩悶するくだりは圧巻としかいいようがない。それでもやっぱり、「先生」の長い長い手紙を読み終わった読者がその最後の頁を繰った際に覚える気持ちは「えっ、コレで終わり!?」だろう。漱石には結局、主人公「私」が同性愛的なものを抱えたまま成長していく道筋が見えなかった。思いっきり感動的な手紙を「先生」に書かせ、それで読者に納得してもらうしかなかった。その5年前、森鷗外が発表した『ヰタ・セクスアリス』では、登場人物が自分のセクシュアリティと自分のキャリアとを結び付けて考えることはなかったが、『こころ』の作者にとっては、それはすでに放っておけない問題になりつつあったということなのだろう。次回はこの小説の神髄にまったく違った視点から迫ります。
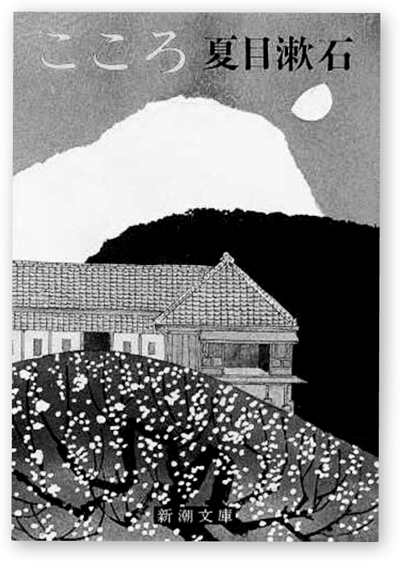
あと数年で定年を迎える大学教員。スペイン語圏の文学、芸能を偏愛。
考えてみると、鷗外のようにアッケラカンと性愛を語る作家はキリスト教世界ではほとんど見当たらない。前回紹介したキューバのアレナスもゲイライフをアッケラカンと語ってはいるが、その背景には、ゲイの存在を認めさせようとする壮絶な闘いの姿勢が感じられる。鷗外のアッケラカンは、やはり、江戸の文化の名残りだろう。そして漱石は……